2025年9月22日、自民党総裁選の公示日。顔ぶれは昨年の総裁選に出馬した候補者のうち5人が再び名乗りを上げた。候補者は政策会見を重ねるが、その矢印は本当に有権者へ向いているのか——。
透明化で止めるのか、実効策へ踏み込むのか
今回の総裁選で「政治とカネ」について各候補から聞こえてくるキーワードは、おおむね「透明化」に収れんしている。だが透明化は出発点に過ぎない。裏金問題を経て失われた信頼は、情報公開の頻度や様式の改善だけでは戻らない。
では、何が”次の一手”なのか。少なくとも以下の三つは、政策集や討論会で具体化が求められる最低ラインだ。
- 資金のリアルタイム電子公開と第三者監査の常設化
- 総裁選資金の収支ルール整備(上限・使途・即時公開)
- 党内処分の基準と適用の可視化(曖昧な「厳正対処」をやめる)
「透明化」は誰もが言える安全ワードだ。問われているのは、痛みを伴う仕組み変更に踏み込めるかどうかである。
なぜ”抽象度”が上がるのか
報道要旨を並べると、候補者別の違いは主に経済政策や野党連携の構えで語られ、「政治とカネ」は抽象度が高いまま扱われている。理由は単純だ。実効策は派閥・資金調達・選挙運動の作法を直撃するからである。
とりわけ総裁選の資金の流れは制度的に見えにくい。ここを動かす意思を明確化すれば、味方の足元にも波紋が広がる。だからこそ、抽象的スローガンでやり過ごす誘惑が強い。だが、その選択は「再生の物語」を掲げる党の自己矛盾となる。自らに厳しいルールを課さない政党が、社会に厳格な規律や負担を求めることはできないからだ。
有権者のサーモグラフ——期待は”透明化+α”
世論の温度は冷静だ。経済最優先のムードの中でも、党再建の必要条件として「政治とカネの決着」を重視する声は根強い。ここには二つの期待が重なる。
- 透明化の定常運転化(ルールとKPIで測れること)
- 違反時の確実なトリガー(処分・返還・公民権制限等の自動発動)
有権者は、言葉ではなく”作動する仕組み”を求めている。すなわち、政治の信頼は「運用」であり「習慣」である。
5人への問い——この一文を政策集に書けるか
候補者に突きつけたいのは、たった一文である。
「総裁選を含むあらゆる政治活動に関わる資金の入出金を、日次で電子公開し、第三者監査の結果を年次で自動公表する」
この一文を政策集に明記し、就任初日から実施できるよう準備しているか。これが、抽象論からの”卒業試験”だ。
経済最優先時代の”政治コスト”
物価高・賃上げ・税制の再設計という重い課題の前で、政治不信は最大の「隠れコスト」になる。なぜか。
政治家が信頼されていないと、どんな政策を打ち出しても「本当に国民のためなのか」「どこかの業界への利益誘導ではないか」という疑念がつきまとう。結果として、国会審議は長期化し、世論の支持を得るのに時間がかかり、政策実行は大幅に遅れる。
企業も個人も「政府の方針がいつ変わるかわからない」「政策の継続性に不安がある」状態では、投資も消費も控えめになってしまう。
だからこそ、経済政策の前に政治の信頼回復が必要だ。政治家が自らの資金を完全に透明化し、「疑われる余地をなくす」ことで、政策議論に集中できる。決定も早くなり、実行力も上がる。
つまり、政治の透明化は単なる道徳論ではない。経済を動かすための実用的な「インフラ整備」なのである。
「解党的出直し」の中身を空にしないために
“解党的出直し”は物語であってはならない。物語は人を鼓舞するが、制度は人を律する。今回の総裁選は、制度に手を触れる意思を示すかどうかが、もっとも鋭敏なリトマス試験紙になる。
最後に——演出ではなく運用へ。透明化ではなく検証へ。言葉ではなく仕組みへ。総裁選が”政治の作法を変える起点”になったと、数年後に言えるように。いま必要なのは、たった一歩の具体化である。
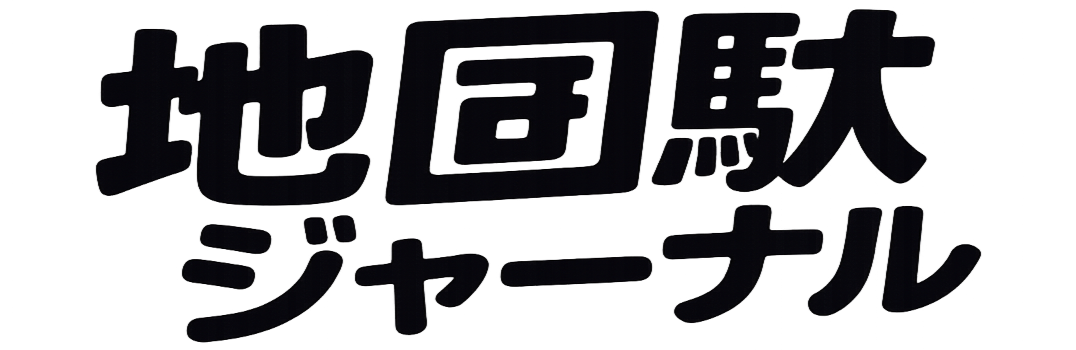

コメント